ねむれない夜に…***in a white night***
ねむれない夜を過ごしているあなたのために、
やはりねむれない夜を過ごしているわたしから送ります。
……ねむれる念を(笑)
TOP > novel
詩のような、小説 ~ある人々の心の連鎖~  ――日々、何のために生きているのか、よく分からなくなる。
――日々、何のために生きているのか、よく分からなくなる。
毎日、毎日、息を吸って吐いて、一体、それが何になるというのだろうか、と。
起きているのか眠っているのかも、ときどき区別がつかなくなるのだ。
女は、ふっと息を吐いた。
擦り切れた畳の上に手足をだらしなく放り出し、寝転んだまま挑むように天井を見据える。
しかし、女の瞳には何も映っていなかった。
女の、氷のように冷たい視線は、眼前の天井を貫いて時空をも超え遥か彼方の過去を彷徨っているようだった。
ふいに、むかし見た写真集のことを女は思い出す。それは遠い国の「白夜」の風景ばかりを集めたものだった。ある人の本棚から見つけたものだ。
眠らぬ白夜の空には星が瞬くことはない。どこまで行こうとも白い世界だ。探しても、探しても星は見つからない。存在自体が消えてしまった訳ではないのに。
――まるであたしの人生みたいじゃないか、と思う。探し物ばかりをしていた自分の人生。
子供の頃、女はとても大切なものを失った。朝、目が覚めたらそれは忽然と消えていたのだ。
果てしない喪失感は、あの日からずっと続いている。
ずっと、ずっと、ずっと――。
喪失感を埋めようと探し続け、必死に足掻いた。何か他に代わるものでもいいと手当たり次第に求めた。
だが、何ひとつ見つけることはできず、手にすることも出来なかった。
虚無感に似た思いが身体じゅうを駆け巡る。女はぎゅっと目を閉じた。
欲しいと思うものは、願えば願うほど逃げていく。すくってもすくっても手のひらから零れ落ちていくのだ。
自分の手には穴でも空いているのではないだろうか――女は目を見開いた。恐る恐る両手を顔の前に持ちあげ、じっくりと眺めてみる。虚しいほど空っぽの手だった。
指がまるで一本一本が意思を持っているかのように大きく震えだした。
震える手指を口元あたりでぎゅっと握る。あまりにも強く握りしめたせいで爪が食い込んで痛かった。
ゆっくりと呼吸を繰り返し、再び指を開いた。
女は自分の手を、じっくりと見つめた。筋張った長い指をしていた。それがどこか人に武骨な印象を与え、どんな色のネイルを塗っても指先がちっとも優雅に見えない。
だが、女はそんな特徴を持つ自分の手指を誇らしく思っていた。それが「受け継ぐものの証」なのだ、と信じていたからだ。この世に唯一無二のものなのだと――。
同時に、女は自分のものではない、もうひとつの手のことを思う。
それは小さなかわいらしい手の事なのだが、可哀そうにその小さな手は長時間泣き続けた為に少し熱を帯びていた。
どんなに握りしめていても、愛着などまるで湧いてこない、うっとおしいとしか思えない代物。
なのに互いの手は溶け合うように次第にしっくりと馴染んでいった。まるで同じ物質で出来ているもののように――女はハッとした。
その小さな手を改めて目の前に持ち上げてみる。
それは、女と同じ「受け継ぐものの証」にどこか似て見えた。
――まさか。
――あり得ない。
――いや、しかし。でも、どうして?
考えたところで、そもそも女に答えが分かるはずがなかった。過去に何があったのか。大人たちはいつも自分から取り上げるばかりで真実は決して語られることがなかったからだ。
だが、この出会いが偶然ではないことだけは確信し始めていた。「血」というものは抗えない。離れていても惹きあうもの――例えば磁石みたいに。女にほとんど直感で真実に迫ろうとしていた。
女にとっては直感というものが、この世に生きることの全てなのだ。理屈など、どうでもいい。
――受け継ぐものの証がもう一つ、ここにあったということだ。
胸に広がる衝撃。女の肩がぴくりと痙攣した。
上体を起こして、そして目の前を、まるで羽虫でも飛んでいるかのように手でばらばたと払う仕草をし始めた。
今度は女は四つん這いとなって、あたりを必死に這いまわる。
なかば躍起になって上下左右に左手をぶんぶんと振りまわしていた。すると、傍らにあったビールの空き缶に手が触れ、カラコロと軽い音をさせて缶はあたりに散らばった。昨晩、三本ほど乾してから、そのまま放置してあったものだ。
女はゼイゼイと肩で息をつき、畳にぺたりと座りこむ。
女はアルコールには強い方だが、ここしばらくは断っていたせいで、缶ビール三本で酔いが回ってしまったようだ。
手足は冷たいのに、頬だけがまだ火照ったようになっている。
女は這いまわるのをやめて頬に手をあてた。ひやりとした冷たさが心地よい。
伏せていた目線を上げると、射してきた白い光に思わず目が眩んだ。窓のカーテンの隙間から白々とした光が差しこみ始めている。
薄明だ。朝日が昇ってくる――。
女は恐れ慄いた。
朝の光は、女からいつも大切なものを奪っていく。目覚めるたびに何かが消えている。今日は何だ―ー。朝、目覚めるのが怖くていつも、いつもいつも眠れることができなかったのだ。
暗闇の中で目を閉じると不意に強い衝動を感じ、覚醒してしまう。
もし、女が普段どおりの精神状態だったならば、ふてぶてしいほど強気に立ち向かっていけたはずなのだ。
だが、今朝だけはどうしても空が明け初めるこの刻を一人で迎える自信がなかった。だから、ぬるくて不味くなったビールでも我慢して飲み続けたのだ。
しかし、感覚は鈍るどころか、より繊細に鋭敏に研ぎ澄まされてしまったようだ。女は諦めたように、ゆっくりと立ち上がった。そして、緩やかに丸みを帯びてきた自分の下腹部をするすると撫でてみる。しかしなんの感慨も湧いてこない。やはり自分は不完全な人間なのだな――と思った。
くしゅん、と小さいくしゃみが放たれた。女は、足元で丸まっていた毛布を引っ張り上げ、それを丁寧に広げた。
それから女は、汗で首に絡みついていた皮の紐を邪魔くさそうに外し、広げた毛布の上に無造作に投げる。
皮の紐に付けられた鉱石の飾りが、ゴツンと鈍い音を立てた。
音のする方へ、女は眼を向けなかった。
だが、心の中では明らかにそちらを意識している。緑色をした石の飾りの方が、女をねっとりと見返しているような気がしていた。
覚束ない足取りで玄関へと向かう。三和土でサンダルをつっかけてから、もう一度、室内を振り返り、ぼんやりとした視線を送る。女の心象そのもののような、家財道具も装飾も全くない部屋だった。
ため息をつき、扉を押して外へ出た。
眼前に長い、長い海岸線が広がっている。
裏里であるこの場所は、女が育った町だった。早朝の海は穏やかに波を打っている。朝凪だ。
太陽が低い位置から顔を出して水平線を赤く染めた。
女は吸い寄せられるようにふらふらと浜辺まで降りて、波打ち際に佇み、赤い水平線をじっと見据えた。
女には、太陽が自分のことをせせら笑いならが昇ってくるように感じられた。
太陽は己の姿を覗かせる前に地上の気温を一瞬ぐっと下げる。一日でもっとも気温の下がる瞬間だ。
その日、一日を規律正しく始めさせるために、地球上のあらゆる邪気を払うべくリセットしている――女は考えている。なんて傲慢なやり方なのだ、と。
「寒い……」
女は、左右の腕で体を包みこむようにして擦った。まるで氷の国に一人、放り出されたようだった。季節はもう清明を過ぎているというのに、また、あたしだけが違う世界に取り残された――そう憤慨しそうになったが、心にふわりと暖かい灯がともった。
――清明。
懐かしい言い回し。女は、うっとりと眼を閉じた。
空に浮かぶ雲の刻一刻と変化する形、うろこ雲、むら雲等そのひとつひとのつの呼び名、何万光年もむこうの星の名前や、二十四節気や自然を表す詩的で奥ゆかしい響きを持った言葉たち。
あの人の愛するものたちだ。
特にあらゆるものが芽吹くこの時季は、あの人の一番好きな季節だった。いつも緩やかに気障に結ばれた唇は、他人が見ればだらしのないと言うのだが、女は、あの人に相応しいセクシーさだ、と思っていた。
その唇から語られる言葉たちは、美しい雫となって女の心に染みていった。雫は、美しい泉となって女の心を満たし
た。女にとって、あれこそが完全な形をなした幸福の日々だった。
けれど、やがて泉は枯渇した。
手のひらではなく、心の方に穴が開いていたのだな――女がそう思った瞬間、キーンという耳障りな音が突如、女を襲った。それは頭蓋骨の中心から発せられている、そんな気がした。続いて感じる頭痛と眩暈。
女は吐き気を催し、よろめいた。
――泉を、再び泉を、満たしたかっただけなのだ。何でもいい。誰でもいい。
何か代わりになるものを、必死に求めていただけなのだ。
けれど、代わりのもので穴を埋めたところで、それが何になるというのか。それはすでに完全になものではないのに。頭の中を、まるで大量のミミズが激しく這いまわっているかのような、不快なざわめきに襲われる。女は叫びだしたかった。――あたしの心はとっくに死んでいたのだ、と。なのに体だけが漠然と呼吸を繰り返している。
――ならば、その呼吸をやめてしまえばいい。
ぴたり、と女の頭の中のミミズが動きを止めた。体の奥底から声が聞こえたような気がした。
「呼吸を、やめる?」
その問いに、我知らず声に出して問い返していた。
海面から突風が吹いて、波打ち際に立っていた女の足もとにザザザと音を立てて波がさざめいた。女の長い黒髪は、ふわりと後ろにたなびいた。
完全なる形というものは、少しでも欠けてしまえば価値がなくなる。
――なのに、自分は何を探していたのだろう、と。
――なにを求めていたのだろう、と。
似て非なるもので埋めようとしたこと自体が間違っていたのだ。完全なるものでないのなら……「そんなもの、あたしには不要だ」
女はサンダルを脱いだ。
そして、足元にきちんと揃える。砂浜に素足を下ろすと、もう寒さも何もかも感じなかった。
ただ、まっすぐに沖を見据えて一歩前に踏み出した。さりさりと砂が鳴き、ばしゃばしゃと水しぶきが撥ねた。
そのまま女は海の中へと、ざぶざぶと前進していく。
足首、ふくらはぎ、太ももまで海水に浸った。女の着ていた白い服は裾から海水を含みはじめた。
さらに一歩、踏み出した時、腹部にズキッと激しい痛みが走った。ズキズキと激しく脈を打つような痛みに、女は息ができなくなった。口を開いているのに、息が吸えない、吐けない。
――これで、ようやく完全になれる。
体中から力が抜けて、女の膝ががっくりと折れた。上体から前のめりこむように海の中に倒れこんだ。
バシャーンと激しい水しぶきがあがり、女の意識はぷっつりと途切れた。
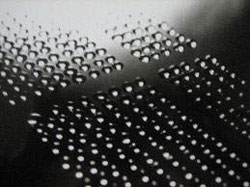 この世に置いて行かれた者の気持ちは、置いて行かれた者にしか分からないだろう。それは、心の時計が永遠に止まってしまうことなのだ。
この世に置いて行かれた者の気持ちは、置いて行かれた者にしか分からないだろう。それは、心の時計が永遠に止まってしまうことなのだ。水平線を眺めながら少女は思う。
早朝の時間帯の、風が穏やかな春の海は少女にとっては儀式の時なのだ。仄暗い海の底から、いつか自分に復讐をしに来るのであろうものに対して捧げる祈り。少女が犯した立証のできない罪。過去の時間の中だけに存在するもの。
だが、少女はその事に対して何ら恐れてはいない。
生まれてきたときから、大して生きていたいなどと思っていないし、いつでも復讐しに来ればいいと思っている。
だが、まだしばらくは止まってしまった時計を見守っていたいとは思う。その時計は少女のものではないが、ただ、どういう終焉を迎えるか見届ける責任はあると思っている。
だから今すぐに立ち去る訳にもいかないのだ。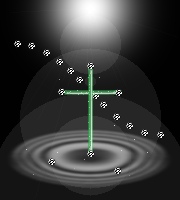
それと、もうひとつ。
少女には、届けなければいけない「欠片」があるのだ。
生まれたときから、いや、生まれる前から心に持っていた「欠片」
それを届けなければいけない。届けるべき相手は、どこの誰なのかを少女は知らない。
けれど、出会えば一瞬で分かるような気がしている。
「理屈」ではなく「直感」でもなく、それは「宿命」なのだ、と――。
ふわりと海風が吹いて、少女の長い黒髪を撫でた。白いワンピースの裾も揺れた。
その時、ふいに視線を感じて少女は後ろを振り返った。
 彼の心は囚われた。
彼の心は囚われた。冷たい光を放つ瞳の少女に。
目も、体も、心も、そして魂も。すべてが一瞬で奪われた――。
彼はときどき悪夢にうなされる。小さなときからずっとだ。
砂浜、冷たい指、強い力。
それはとても断片的で、目が覚めても内容はひとつも覚えていないのに、冷や汗をびっしょりとかいて徒労感だけが体に残っている。
どこかへ導かれようとしている――その感触だけは、何故かリアルに覚えてるのだ。
ある朝、胸苦しさに襲われて耐えきれなくて外へ出たら、その視線の先に、ある少女がいた。その姿は、まるで置き去りにされた子供のようだった。
実際に、少女は置き去りにされた子供だったのだけれど、あれから時が過ぎ、不思議なめぐり合わせで少女は彼の人生にひっそりと同居することとなった。
見飽きるほど当たり前に、手を伸ばせば届く距離に。
そのきっかけを作った彼の父親に、彼は腹を立てるべきなのか、喜ぶべきなのか、どう表現していいのか分からなくなる。もしかしたら、そのどちらも、ぶつけるべきなのかもしれない。
しかし、そもそも何の感情も湧きあがってこないのだ。まるで心の中から感情が欠落してしまったように。
強いて言えば苦しいのかもしれない、と彼は思う。目を閉じても、いつも浮かんでしまうのだ。
灰色の海、白いワンピース、黒い髪、そして冷たい瞳とありったけの警戒心。それは繰り返し見る悪夢の続きにも
似ているのに、どこか神々しくも見え、とても眩しく、まぶたの裏に閃光のように焼き付いていて、すごく、すごく痛かった。
今では彼の前でも、少女は糸がほどけたように軽やかに笑う。しかし、彼は少女に触れることができない。ただ、安らかな寝顔をそっと見つめるばかりだ。彼の手は空間を彷徨った。長い手指をした左手を。
このまま時間が止まってしまえばいい――と何度も願った。せめて、ずっと見守っていられるように、と。
彼の心はがんじがらめになって、もう二度と動くことができない気がしていた。
喉の奥が熱く、痛い――彼は必死にもがいていた。
あともう少しで、彼の閉じ込められていた感情と記憶が解放される。だが彼自身はその事はまだ何も予感すらしていなかった。
 彼は、どうやら本当に覚えていないようだ。
彼は、どうやら本当に覚えていないようだ。彼がくりかえし見る悪夢、それは遠い「記憶」なのだ――と。
彼女はとうの昔に、そのことに気づいているのだが、どうしても彼にそれを言い出すことができない。
 二人がまだ幼い頃に、彼が消えてしまわないように、ずっと手を握っていたのは自分なのだ、と。
二人がまだ幼い頃に、彼が消えてしまわないように、ずっと手を握っていたのは自分なのだ、と。
自分が沈んでしまいそうな時に、ずっと手を握っていてくれたのは彼なのだ、と
自負。
そのことだけが、彼女の唯一の支えだった。
彼女は、彼と共有した時間の長さで勝とうとしていた。
今まで頑張ってきたこと、それをここで簡単に放棄する訳にはいかないのだ。
でも、もう限界なのかもしれない――彼女の心は折れそうだった。
彼の心は完全に囚われてしまっている。少女の存在に。それはもう揺るぎないことだ。
心の鍵を持っているのは、自分ではない――そう認めざるを得ない。
溢れでる涙を彼女は止めることはできなかった。
なぜか、いつも別れは病院においてでした。不思議な縁に苦笑いしか浮かんできません。遡ってみれば、ある人との出会いがすべての始まりでした。
ひとりの男をめぐり、ある女性はその愛する男の子を産みました。だがある一方でもう一人の女性は、その男の事を生涯求めて、その苦しさに耐えきれず存在を消してしまいました。ただし、置き土産をたくさん残して――。
この世に生まれてくる命というものは、何もかも愛おしいと思っています。自分が望めないものだから、余計にそう感じるのかもしれません。だから2人に代わって一生をかけて守ろうと心に決めたのです。彼らを手元に置こうと決めたのは、掛け値なしでその事が理由の全てでした。
この世に生ける人々はみな自分の子供のように思えます。血ではなく、人種も関係なく。世界中を旅して、いくつもいくつもファインダーに収めきました。ひとりひとりがオンリーワンの美しい宝のように思えたのです。
けれど「血」というのは侮れないものなのですね。その事を思い知らされました。彼らは互いの存在すら知らなかったのに磁石のS極とN極のように、ぴたりと寄せ合ってしまったのです。まさか彼らが、こんな風に出会うとは思ってもいませんでした。ましてや、自分の人生にそんな風に絡んでくるなど、と。
昔、ある女性に贈った美しく野性味あふれる鉱石、その石の名前と同じ名前をした少女は、その女性に似て冷たい目で人の心をやすやすと奪います。脆く、危うく――です。まるで女が、少女の体の中に同居しているかのように思えることがあります。結局、二代に渡って心をバラバラにされてしまいました。
自分のエゴが招いた結果なのでしょう。介入者でしかありませんでした。そのことで「子供たち」を巻き込んでしまったのかもしれません。自分だけが苦しめられるのなら一向に構わなかったのですが。
子供たちにはこれ以上傷ついて欲しくはないと思っています。ですが、それこそ彼らにとって必要なものだったのかもしれません。彼らは傷つきながらも、お互いをどんなに必要としているのか傍から見ていて痛いほどに分かるからです。互いの忘れものを届けに来たのでしょうか。遠くにいようとも、近くにいようとも、心で繋がっているようです。
結局、どこへいようともいずれは引き合う運命だったのでしょう。彼らの共鳴は、時に痛々しく見えますが私には美しい音楽のように心に響いてきます。
やはり止められないでしょうね。彼らを愛すことを、彼らを見守ることを。
今、自分が生まれたことの意味が見出せなかったとしても――
今、人を愛することを初めて知って途方に暮れていたとしても――
今、人に依存することを捨て、ひとりで生きる勇気を持とうとしている者も――
少し休息が必要なようです。けれど、やがて、みな目を覚まして立ち上がることができることでしょう。
神様はその人が乗り越えられる試練を与えるのかもしれません。
それがどんなに大きく苦しくとも、逃げずに精一杯、生きるべきです。この世の中に生きる一人ひとりが全員で美しい調べを奏でているのですから。誰が欠けてもいけないのです。
その先には、みんなの分だけの輝かしいく新たな世界が待っているのですから――。